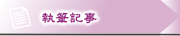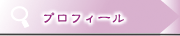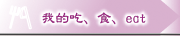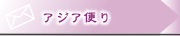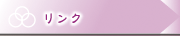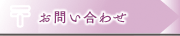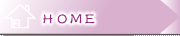この本の存在を知ったのは偶然だった。ときどき見ている林真理子のブログで紹介されていて、何気なく買ってみたことがきっかけだった。私は「食べることが好き、台湾も好き」。ただそれだけの理由で、本書を手に取ってみた。しかし、最初に開いた著者の長男が書いた「母の思い出」を読んで号泣…。「なんていい本なの〜」。しばし呆然となって、もう一度同じところを読み返し、「これ映像化できるよね〜」などと思いながら、冒頭からじっくり読み始めた。すでに私の頭の中には(見たこともないのに)日本統治時代の台南の風景がくっきりと浮かんでいたのだ。
著者は台湾出身の料理研究家で、NHK[きょうの料理]などにも出演していた人らしい。しかし、1933年生まれで、2002年にはもう亡くなっており、私の記憶にはない。(この本は1986年に文芸春秋から出版されており、今回文庫化された)。そもそも料理研究家という職業は、最近脚光を浴びるようになったもので、以前はごくわずかな人しか表に出てこない職業だった。その料理研究家によるエッセイ本だ。
「安閑園」というのは著者が幼少時代の大部分を過ごした台湾・台南市郊外の大邸宅のことで、この本では、そこで大家族とともに過ごした日々の出来事や料理のことが綴られている。豪邸にいつも宝石を訪問販売しにきていたおばあさんのことを書いた「宝石売りのおばあさん」、台湾総督府の要職にあり実業界でも名を馳せた大物でもあった父親のことを書いた「父の誕生日」、家族ぐるみで懇意にしていたお医者さんのことを書いた「二人のお医者さん」、日本人には馴染みの薄い「内臓料理の話」等々。
一つひとつのエッセイは主に料理中心ではあるのだけれど、そのままストレートに書いてあるわけではないので、「まゆつばごっくん」という類の料理本ではない。むしろ食べ物の話をふるために両親や兄弟、お手伝いさん、周囲の人々との日常会話や生活のこまごまとしたこと、家族の出来事が生き生きと書かれていて、まさに辛家という一つの家族の最も輝かしい時代を描いた壮大な物語になっているのだ。
著者の父親の辛西淮という人は中国・福建省の出身で、幼い頃に両親とともに台湾に渡った。日本植民地時代、台湾総督府の要職にあった人で、鉄道事業などでも成功した実業家だったという。私の友人が所蔵する「台湾人名録」にも名前が載っていたというから、相当な大物だったらしい。もちろん破格のお金持ちでもあった。その実業家でもあり、家長である父親が中国の伝統的な家庭の中でどのような役割を果たしてきたか、どんなに仏様を大事にしてきたかが文章の中によく現れている。また、母親の役割、母親が下人に対してどう接してきたか、主婦として大家族の食事の準備をどう段取りしてきたか、お祝い事での風習をどうしてきたか、などもよく描かれており、この1930−50年代の台湾の名家の生活というものがよくわかる。そういう意味では文化人類学的にもこの本は貴重な資料になるのではないかと思う。
そうした貴重な情報とともに、私はこの本を読んでいて単純に、何度も目頭が熱くなってしまった。別に悲しいことが書いてあるわけではないのに、何度も、何度も涙が出た。もちろん、著者が20歳で日本に渡り、離婚し、息子と二人でつつましく生活していたことは書いてあるのだが、そこに暗さやみじめさはひとつもない。それが悲しいのではないのだ。むしろ誇りを持って明るく生き、日本という国から故郷のなつかしい日々を回想している。だが、そこにはありあまるほどの家族への愛情、台湾へのノスタルジーがつまっていて、その温かい目線が行間に現れていたのかもしれない。「お嬢さん」「奥様」としての人生を歩まなかった著者の毅然とした態度こそに、私は感動したのだ。結婚することのなかった医者との数十年後にわかった「秘話」のくだりでは、人生の分かれ道とは一体何だろう……と考えずにはいられない。
各エッセイの後ろに紹介されている料理レシピも気になる。この著者が今生きていたら、どんな料理を作ったんだろう。どこかで私たちも口にすることができたのだろうか。そう思うと料理は書籍のように書棚に「保存」しておくことができないものだけに、心底残念だ。今度、自分でも辛家に伝わる料理をひとつ作ってみよう。そして台南に行ったら、郊外に立派な邸宅が残っているのか、ぜひ自分の足でみたい。(2010年11月11日)
|