

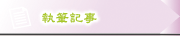
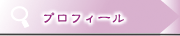
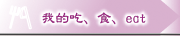
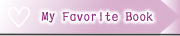
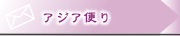
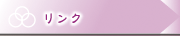
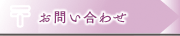
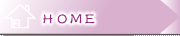
|
2005年4月17日号「Yomiuri Weekly 」(読売新聞社発行) P48−50 李涛 Li Tao (劇団四季・俳優/中華人民共和国出身) 満月が青白く輝く夜、街の片隅のゴミ捨て場に24匹の野良猫たちが集まってくる。そう、今宵は年に一度の舞踏会―。 今日もまた、劇団四季のミュージカル「キャッツ」の幕が開く。人間に飼い馴らされることを嫌い、たくましく生きる野良猫たちが次々とステージに現れる。夜を徹して歌い、踊ったそのあとに、長老猫が天上に上る最も純粋な一匹のジェリクルキャッツを選ぶという物語。円形のステージを囲む観客席ではファンが期待に胸膨らませている。 中国出身の李涛が「キャッツ」で初舞台を踏んだのは2002年3月28日、大阪MBS劇場だった。李の役名はマンゴジェリーという赤毛の泥棒猫。以来、李は東京など各地で舞台に立ち続け、今年2月末までの出演回数は412回を数えた。また、2004年6月からは「ライオンキング」の主役、シンバにも抜擢された。入団4年目にして、劇団四季の看板を背負って立つ俳優陣のひとりとなった。 2月下旬、夜公演を終えたばかりの李は「キャッツ」の衣裳とは打って変わって、さわやかな私服姿で現れた。ふだんからおしゃれには気を遣っているように見えるが、あまり休日はないという。 「『キャッツ』の公演は昼と夜の1日2回か、または1回です。毎週月曜日が休演日ですが、休日はマッサージに行ったりするので、完全な休みというのはほとんどないですね。身体のケアを第一に考えて生活しています」 劇団四季の「キャッツ」は21年間、ロングラン・ヒットを続ける。数多くのファンが楽しみにしているだけに、体調管理は俳優にとって最も大切な仕事のひとつだ。 もちろん、公演期間中でも歌や踊りのレッスンは欠かせない。発声練習や柔軟体操、メンバー入れ替えなどにともなう細かな動きのチェックもある。 なかでも、李が注意しているのが日本語の発音だ。中国生まれ、中国育ちの李にとって日本語は外国語。「完璧な日本語」をマスターするのは並大抵のことではない。 「セリフの多い『ライオンキング』のシンバをやっているときなどは、夢に見ることもあります。本番でセリフをかんじゃったらどうしようって。いつもすごく心配になるんですよ」 生まれ故郷は甘粛省・蘭州。シルクロードへとつながる内陸部の都市だ。ここで12歳まで過ごし、親元を離れてひとりで北京のダンス学校に入学した。歌やダンスが大好きだった母親の薦めだったが、しだいに李自身も夢中になり、北京舞踊学院で民族舞踊を学んだ。 来日のきっかけは大手プロダクションのスカウトだった。大学でライブをしていたハンサムな李に、北京を訪れていた日本のスカウトマンが声を掛けたのだ。 「アジアのスターにならないか」と誘われて心が動いた。大学卒業後は中央歌舞団への入団が約束されていたが、安定した中国政府お抱えのダンサーになるよりも、未知の可能性に惹かれた。 プロダクションが横浜市のアパートを準備し、日本語学校で日本語を学ぶ日々。生活の心配はなく、スターへの階段を歩み始めたかに思えた矢先、思わぬ落とし穴が待っていた。プロダクションが国際事業を縮小するというのだ。 「アメリカへ行くか中国に帰ることを薦められ、そのために支援もしてくれるというのですが、当時の僕にはピンとこなかった。香港で歌手になれないかと思い、香港に渡りました」 だが、現実は厳しかった。レコード会社9社の担当者と会い、日本語と中国語で歌ったポップスのデモテープを聴いてもらった。好感触を得るものの、最後に聞かれるのは決まって「国籍はどこ?」。中国国籍では台湾などでのプロモーションがやりにくい、というのだ。 仕方なく北京に戻った。夢破れて、という感じだったが、結局この帰国が李をミュージカル俳優へと導いてくれた。北京でダンスを続けていたとき友人から「劇団四季のオーディションを受けてみないか」と誘われたのだ。 劇団四季は「李香蘭」などの昭和3部作があるように、アジアを舞台にしたオリジナル・ミュージカルにも力を入れている。97年ごろから身体能力が高い中国人や歌唱力が抜群の韓国人など、アジア人を積極的に採用し始めていた。 2001年秋。入団を機に、李は再び日本の地を踏んだ。 「歌だけでなく、歌って踊りもできるミュージカルは自分に合っていると思いました」と語る李だが、入団後、苦労したのは「舞台での日本語」の習得だった。 日常会話の日本語とは違い、舞台上ではわずかな発音ミスがまったく違ったセリフに聞こえ、ストーリーを誤解する恐れがある。それだけでなく、「外国人がしゃべっている日本語」だとわかると、日本の観客は敏感に反応し、興ざめしてしまうのだ。 李は日本語と中国語の発音の違いについてこう説明する。 「中国語では舌を上あごにつけたり、舌を巻いて発音することが多いのですが、日本語は『らりるれろ』のように舌を巻いても軽くパタパタするだけ。20年以上も口の中で舌を巻き続けてきた僕にとって(笑)、日本語のセリフを日本人と同じように自然にしゃべることは至難の業でした」 練習のため、セリフはすべてノートに書き写し、日本語の先生にアクセントとリズムの記号を書いてもらう。先生のあとについて何度も繰り返し練習する。ようやく正しく発音できても、ダンスと一緒にセリフを言おうとすると、注意がそれて発音が崩れてしまう。しかもミュージカルではセリフに感情を込めなければ意味がない。 歌と踊りとセリフ。日本人でも難しいこの3つをマスターしようとひたむきに努力していた李を「ライオンキング」で共演した俳優の中嶋徹は今も鮮明に覚えているという。 「僕が話す日本語の口の形や、口の中で共鳴する部分を一生懸命に真似て、研究していましたね。もともと彼は耳がいいのですが、それに甘んじない。すごいがんばり屋です」 自分の話す日本語が日本人に違和感のない日本語に聞こえているかどうか。大人になってから日本語を覚えた李にとって、不安は今でも解消されないという。 「だから繰り返し、練習するしかないんです」 劇団ではビデオなどで動きを覚えるのではなく、舞台の上で実際に共演者たちとともに動き、身体でダンスと歌を覚えていく。 「『キャッツ』の場数を重ねてきて、自分のマンゴジェリーができ上がってきた気がします。マンゴジェリーってどんな猫なのか。どんな性格なのかって。やればやるほど、作品のテーマについてもじっくり考えるようになりました」 歌や踊りが楽しいだけでなく、作品で訴えたいテーマを観客に伝えることができれば成功だ、と思っている。 李は初めてマンゴジェリー役をもらったとき、コンビの猫役だった元団員、松永さち代に言われた言葉が忘れられないという。 「今日が自分にとって最後の舞台になるかもしれないという危機感を持つこと。たった一度の人生をたくましく生き抜くキャッツのように、李涛も李涛らしくがんばってね、と励ましてくれました。だからいつも今日で最後、と思って舞台に立っています」 「キャッツ」に登場する24匹の猫はそれぞれが魅力的な個性を持っている。派手なメーキャップの下の俳優の素顔もまた、個性的だ。李涛は李涛らしく。修練を重ねた日本語は、もはや弱みではなく、今や武器として李を支えている。 文・中島恵 |
Copyright(C) 2009 Kei NAKAJIMA. All rights reserved.
