

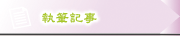
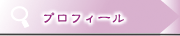
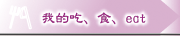
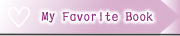
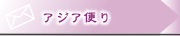
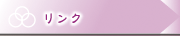
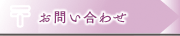
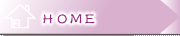
|
2003年6月15日号 『Yomiuri Weekly』(読売新聞社発行) p.16〜19 香港ブームから10年 海を渡った日本人OLたちは今ー 多くの日本女性が、能力主義で男女差別がない香港に理想を求め、夢を追ったOLの香港ブーム。あれから10年以上がたった。香港は中国返還セレモニーという世紀のイベントを境に、経済が悪化し、日本同様、景気の底からはい上がれないままだ。その間に、彼女たちはそれぞれの人生をどう過ごしたのだろうか。その胸のうちを聞くと、現代ニッポン女性の1側面がリアルに表れてくる。 (写真・文 中島 恵) 皇太子ご夫妻が、ご結婚された1993年。バブル経済が崩壊し、日本中にどんよりとした空気が漂い始めた頃。塩河美砂さん(当時29)は四国の公立中学校で教壇に立っていた。国立大学の教育学部を卒業し、社会科の教師になって7年。校内暴力が吹き荒れる中での教師生活に疲れ、30歳を目前に日本を飛び出したいと思っていた。 香港島からフェリーで約20分、ディスカバリーベイの船着き場で私を待っていてくれた塩河さんは、現在39歳。均等法第一世代だ。かたわらに立つのは今春結婚したばかりのご主人。塩河さんは94年に香港大学に留学、その後も香港に残り、日系の学習塾、香港系インテリア会社など、それまで日本で経験したことのない仕事にチャレンジしてきた。「何年まで、と決めてきたわけではありません。香港返還も別に関係なかった。日本で教師をしていたときは365日、生徒や授業のことを考えていた けど、香港に来て広い世界を見ることができた。仕事は生活のためだ、と割り切れるようになりましたね」 教壇で必死の形相で生徒を叱っている自分の夢を見なくなったのは、つい最近のことだ。幼い頃からまじめで、勉強もよくできた。日本では周囲の目もあり、常に「何かをしなくちゃ」と走り続けてきた自分が、香港で変わることができた、と塩河さんは語る。「日本人独特の人間関係のしがらみに悩むことがなくなり、気持ちが楽になった。でも、香港にきたとき、同年代の女性たちを見ていて、40歳過ぎてもここで頑張り続けるのかなって思った。私はもし香港で結婚しなかったら、日本に帰っていたかもしれない。40歳を過ぎて一人で異国にいるのはしんどいと思う」 (中略) 10年前、週刊誌には「棄国子女、香港へ」などのタイトルで特集記事が組まれた。女性をお茶くみか花嫁候補にしか見ていない男性社会に見切りをつけて、海外雄飛した女性たちのことをこう呼んだのだ。でも、帰国後の彼女たちの生活や考え方は表立って見えてこない。 11年間住んだ香港から去年帰国したのは石川ゆみさん(仮名・36)大学の中国語学科を卒業し、総合職として都銀に入行。だが、能力に応じた仕事を与えられず、91年に香港に留学。93年に日系A銀行で初めての現地採用枠で入行した。日本人駐在員と肩を並べて仕事をしたが、バカにされ、何度も悔しい思いをした。その銀行は96年に大手B銀行と合併。香港支店は一時800人を超える 大所帯となったが、日本の金融不安を反映して企業体質は悪くなる一方だった。 石川さんは言う。「すべてにおいて日本のカルチャーを持ち込んでいる。バブル崩壊後5年たっても、ぜいたくな暮らしぶり、なあなあの日本企業の体質そのままだった」。本社から役員がきたときに、ろくに英語もできない駐在員が役員に向かって「現地採用者はぼくが監督しているから大丈夫です」と言ったときには、あきれて開いた口がふさがらなかった。給与交渉でも上司に直談判したが、希望はかなわなかった。しかし、それでもエネルギッシュな香港での自由な生活は満足のいくものだった。 石川さんに変化が出てきたのは32歳の頃からだ。派遣されてくる駐在員の中に、自分より年下がいることに気づいた。自分が40歳になったとき、このまま勤め続けることができるのか。どんなに仕事ができても、現地採用では駐在員のポストを超えることはできない。40歳で帰国したとして、自分に合った仕事が日本にあるのだろうか?香港にきて、初めて立ち止まった瞬間だ。 24歳で海を渡ってから10年。若いと思っていた自分が急に年を取った気がした。香港は、元気でバリバリ仕事をしたい人にとっては最高の場所だ。でも、転職し、別の道を模索するエネルギーはもうなかった。同時に香港人のいい加減さや、香港製品の粗悪さが鼻につくようになってきた。若い頃は100円ショップで買ったもので満 足できたのに、年を重ねてくると、いいサービス、いい製品を体が求めるようになる。一時帰国して日本を旅行してみると、温泉やレストランが一流のサービスでもてなしてくれることに、いたく感激した。日本は成熟し人々に覇気はないが、最高級のモノが何でも手に入る国だと思った。 そんなとき、梅畑を経営していた実家で祖母が倒れたという電話が入った。代々農家で、家族で守ってきた梅畑だ。長女である自分が帰らなくては、と思ったのが帰国の引き金になった。香港を嫌いになったわけではない。でも「香港は、もういいかな」。自分に言い聞かせた。帰国前日まで勤めていたので、感傷にひたる暇はなかった。友人たちは突然の「帰る宣言」に驚き、あわてたという。「みんな、私が永住すると思っていたみたい。今まで多くの日本人女性を見送ってきたけど、ついに自分も見送られる番がきちゃった」 ちょっと寂しそうだった。香港に未練はないか、と聞くと「半分、半分」と石川さんはつぶやいた。銀行の仕事は大変だったが、10年も勤めた会社を辞めたことは惜しいと思っている。忙しかった日々や香港のギラギラしたネオンも、今ではなつかしい。帰国後、石川さんはしばらく友人との接触を避けた。「これから日本で何するの?」この質問が大嫌いだったからだ。日本しか知らない友達に海外生活を話すと、自慢に取られそうで恐かった。それに自分の気持ちは、おそらく理解してもらえないだろうと思った。今年。石川さんは思いがけず結婚して長野に移り住み、新生活をスタートさせている。 |
Copyright(C) 2009 Kei NAKAJIMA. All rights reserved.
