

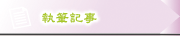
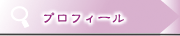
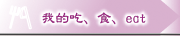
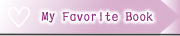
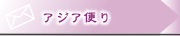
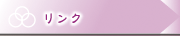
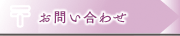
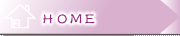
|
ブライアン・バークガフニ 「長崎へゆこう」 1982年、やわらかな薫風が頬をなでる5月の早朝。剃髪し青々とした頭に、小さなカバンひとつをぶらさげたブライアン・バークガフニは、京都・妙心寺から一路、国鉄長崎駅を目指していた。 洗いざらしのジーンズをはいた碧眼の僧侶は、この2年前にお寺の用事で数時間だけ訪れた長崎のことがどうしても頭から離れず、白紙の状態で長崎行きを決意したのだ。 あれから20余年―。長崎に腰を落ち着かせたバークガフニは、縁あって9年前に長崎総合科学大学の教授となり、「長崎学」の第一人者と呼ばれるようになった。グラバー園ゆかりのグラバー一族について、国際墓地に眠るイギリス軍人や若き水兵、めがね橋など。研究テーマは比較文化論、長崎の国際交流史だが、カバーする人物や歴史など、守備範囲は実に幅広い。 大学での講義はちょっとユニークだ。たびたびフィールド・ワークに出かける。たとえば、学生に昔の長崎の絵葉書を見せて、長崎市内のどこなのか、同じアングルの場所を探させ、地域の変遷や歴史について発表するという具合だ。 市民講座の講師もつとめ、参加者を国際墓地に案内するツアーを行っている。各種団体から請われて講演をする機会もめっきり増えた。今やバークガフニは、長崎で最も有名な外国人のひとりだ。 南山手の坂の上に建つグラバー園から、長崎港を見下ろしながらバークガフニは言う。 「私は自分と同じように長崎に魅せられ、この地で亡くなった先人たちの思いを知りたくて、彼らの足跡を辿ってきたのかもしれません。長崎は東洋と西洋が自然体で調和している、日本で唯一、不思議な魅力にあふれる町。それは昔も今も変わりません」 バークガフニはカナダ出身だが、珍しい苗字はアイルランド出身の祖父に由来する。バークガフニ一家は多くのアイルランド系移民がそうであるように、敬虔なカトリック教徒だった。親戚にはイエズス会の神父もいる。だが、彼自身は、カナダの大学時代、友人とのふとした会話から仏教に興味を持ち、東洋の文化と宗教、禅への関心を膨らませた。大学を休学し、ヨーロッパ経由でインドへ。5ヶ月間インド各地を放浪したのち、日本の地を踏んだ。 「禅の修行をしようと、紹介を得て、最初は愛媛県の小さな禅寺に入りました。禅とは何か。真髄を知りたいと思って」 寺の老師につき午前5時に起床。読経、掃除や座禅を組む修行の日々を送った。そして臨済宗妙心寺派の大本山、京都・妙心寺の専門道場に入門。日本で最も厳しいとされる禅寺で、雲水としておよそ9年のときを過ごした。 「禅の修行を積むことは、キリスト教とは何なのかを考えるきっかけになりました。それまでの僕は、キリスト教は外にいる神様に祈る、というイメージしか持っていなかったのですが、座禅をすることで、祈りとは自分の内側にあるもの、ということに気づいたのです。スタイルが違うだけで、キリスト教と仏教は相反するものではない、とも思うようになりました」 しかし、修行8年目ごろになると、ジレンマを感じるようになった。 他の雲水たちには、修行がライフワークで、いずれどこかの住職になる。だが、西洋人で禅の修行をしてきた彼は住職になりたいわけではなかった。自分は日本人の雲水とは違う。もやもやとしたジレンマを抱えていたとき、以前一度だけ訪れた長崎に急に行ってみたくなった。 「たとえば、めがね橋の存在です。西洋生まれの石橋なのに、何の違和感もなく長崎の町にすっかり溶け込んでいる。東洋と西洋の無造作な調和は、ジレンマを抱えていた私にとってとても理想的なもの、魅力的に見えたのです」 そして、寺を出た。長崎大水害の直前から、めがね橋近くに下宿し英語教師や翻訳のアルバイトで生計を立てた。やがて興味を持った長崎の文化や歴史をコツコツと独学で調べ始める。 長崎市職員として原爆資料館の英文展示の仕事などをバークガフニに依頼していた旧知の山口洋一郎はこう話す。 「被爆者の手記を英文にする作業などでお世話になりました。勉強熱心なのに、ぶったところがなく、謙虚な人です」 85年に開催された「世界平和連帯都市市長会議」の際、通訳をしたのが縁で元島等・長崎市長(当時)と知り合う。不安定な生活をするバークガフニを思いやった元島の推薦で、外国人として全国で初めて市の嘱託職員に抜擢される。以来、本格的に歴史研究の知識を蓄積していくことに。だが、気づいたのは長崎の歴史研究がほとんど手つかずの状態であることだった。 「国際墓地は長崎市に3ヶ所ありますが、意外にも墓地は荒れ放題でした」 シーボルトや出島は多くの学者が研究しているのに、グラバー園や国際墓地など旧居留地はなぜ研究対象にならなかったのか。 「私の想像では、『居留地』の存在そのものが日本人にとって好ましいものではなかったから、だと思います。それに言葉の問題。居留地の資料は外国語ですから、日本の郷土史家にとって厄介だった。歴史博物館を見ても、江戸時代までの研究はさかんですが、明治以降の長崎は取り上げられていない。神戸や横浜にも居留地がありましたが、空襲で焼けてしまっている。そういう意味でも、長崎ではまだ調べるべきことが多いはずなのですが」 グラバー園に関してもそうだ。グラバー邸の所有者だったスコットランド商人のトーマス・ブレイク・グラバーは1859年)、21歳で長崎に降り立ち、薩摩藩などと接触。武器や船の商売で巨万の富を築いた。豪奢な洋館など観光面ばかりにスポットが当たるが、グラバーが流暢な日本語を話し、外国人として最高の勲二等旭日重光章を受章したことなどその人生はあまり知られていない。 ここ数年、バークガフニのコツコツとした研究が書籍になり、インターネットが普及したことで、「うれしい研究の副産物」がいくつも舞い込むようになった。 「ある日突然、アメリカの女性から『祖父が長崎に住んでいたようなのです』というメールがきました。調べてみると、それはロバート・ボーイという医者で坂本国際墓地に埋葬されていた。でも、親族は爆心地に近いのでお墓はないだろうと思い込んでいた。事実を知って来日した際、もっと早く知っていれば、ととても残念がっていました」 のちに兄のヘンリー・ボーイが横浜に住んでいたことがわかり、その孫がシャンソン歌手の平野レミさんであることなど系譜も判明した。 「分断された過去の歴史や無縁仏を研究しているのではなく、長崎の歴史研究は今を知ること。今に続く人間の”生きた証“を調べているのだ、と痛感しました。僕の研究が長崎に骨を埋めた人々への供養になっていたとしたら、うれしいですね」 取材で訪れたとき、バークガフニは2月初旬に出版した新刊「華の長崎」の最終作業に取り組んでいた。世界各地に残されていた長崎の絵葉書を5年がかりで収集し、解説をつけたものだ。 長崎文献社専務で編集を担当した堀憲昭は言う。 「ブライアンさんの所有するファイルを見たとき、編集者の勘で『これだ』と飛びつきました。ブライアンさんは長崎にとってかけがえのない人です」 明治、大正、昭和の華やかな絵葉書の1枚1枚を、少年のような目で見つめるバークガフニ。キリスト教と仏教、西洋と東洋とがこの島国で出会い、融合してきたのか。そして今は―。長崎という歴史の「実験工房」でバークガフニの探求は続く。 文・中島恵 |
Copyright(C) 2009 Kei NAKAJIMA. All rights reserved.
