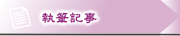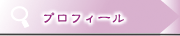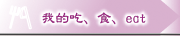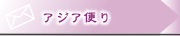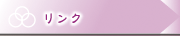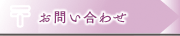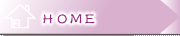書評を読んで手に取った1冊。今年の私の読書ベストワン。ベトナム戦争ものにはこれまであまり関心がなかったが、大宅壮一ノンフィクション賞を受賞したと聞いて、読んでみようと思った。分厚い上下巻で最初は読みきれるかなと思ったが、ページをめくったとたん、すぐに平敷さんの描く独特の世界に引き込まれていった。
内容はベトナム戦争という題材を取り上げてはいるが、実際にはベトナム戦争の是非や客観的な国際関係を綴ったものではなく、ベトナム戦争に関わったカメラマンや記者などに関するごく個人的な回想録である。著者は1938年、沖縄生まれで、大阪の関西テレビに就職し、ベトナム戦争の報道をしたいと退職した経歴を持つ。1966年から75年のサイゴン陥落まで、アメリカのABC放送のカメラマンとしてベトナム戦争に従軍した。最初はろくに英語も話せずに苦労したようだが、しだいに手柄を上げられるようになる。その過程で知り合ったアメリカ人の上司や同僚、他社のフリーランスの記者たち、ベトナムで一旗挙げようとした日本人のフリーカメラマンたちとの思い出が、戦争の細かい描写とともに描かれていく。その中には、ニューヨーク本社の考え方、ベトナム報道のあり方、現場では何が起こっていたか、アメリカ人のものの考え方、戦場で運を使い果たさない教訓、ベトナム人の助手との交流など、ありとあらゆるものも詰め込まれている。また、東洋と西洋、勝者と敗者、加害者と被害者といった構図も浮き彫りになっている。卓越していると感じるのは、戦場での一つひとつの描写だ。のちのインタビュー記事を読むと、著者は放送カメラマンで、ムービーをつねに回し続けており、その記録があったから細かい描写を描いたり思い出したりできた、と話しているが、それにしても、この細かい描写力はすごい。大宅賞受賞の際、立花隆さんが「文章が下手」と書いていたが、荒削りでも、これだけのするどい描写は経験した人でなければできないものだと思う。どんな上手な文章よりも人の胸を打つのだ。
上下巻のうち、上巻で唯一私が知っている人物といえば、日本人カメラマン、沢田教一だ。ピュリツアー賞を受賞したことで、日本でもカリスマ的な存在となっているカメラマンである。その沢田との出会いもおもしろいのだが、驚いたのは、そのほかに数々の無名の日本人カメラマンがベトナムに渡っていたという事実だった。全然知らなかった。沢田以外に出てくる有名な日本人は開高健だけで、新聞社から派遣された駐在員の記者はひとりも出てこない。あの近藤紘一すら、である。それだけ平敷さんは日本人とつるまず、現地に溶け込んでいたのだと感じた。しだいにおもしろさが増して迫力が拡大していくのは、断然、下巻である。しだいに戦争終結に向かう中、大親友のシンガポール人カメラマン、テリー・クーとの別れの場面では、涙が止まらなかった。サイゴン陥落の直前の出来事だった。最終章では、仲間たちのその後が描かれている。ある者は亡くなり、ある者は消息もわからない。「キャパになれなかったけれど、がっかりしていない」という平敷さんの心が痛いほど伝わってくる名著。これからも折に触れ、読み返したいと思う。(2009年9月2日)
|